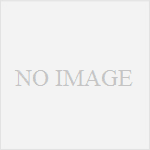膨大な知識を求められる中学受験、その対策は?
中学受験では理科や社会を中心に、『膨大な知識量』が問われます。
確かに小学生の頃というのは、脳がスポンジのように柔らかく、たくさんのことを覚えることができる年代なのですが、大人が考えてもこれだけの量を覚えていくのって大変だよなぁって思ってしまいます。
実際の入試問題も大人顔負けの難易度で、知識量を武器に合否が決まる場面も少なくないというのが現状です。
とはいえ、すべてのお子さんが「覚えるのが得意」というわけではありませんよね。
さて、残念ながら、私自身はあまり覚えることが得意ではありません…(-_-;) 有能な文系の同僚の言葉の端々などから、よくそんなことまで覚えているなぁ~と関心してしまうことがよくあります。
そのため、覚えるのが苦手な子への同情を禁じえません・・ (^_^)
大切なのは、「どうすれば記憶に残るか」を工夫すること。それもできれば、無理に覚えるのではなく、少しでも「楽しい!」と思える方法で進めていくことが、長期記憶の定着にもつながります。
『楽しく覚える』ことで、記憶力がグッと高まる!
放っておいても覚えてしまうような記憶力に長けている子はいいのですが、私のように覚えるのが苦手な場合、できるだけ記憶が定着するように工夫する必要があります。
そのためには、今まで申し上げているとおり、『繰り返す』ことが王道だと思います。
しかし、今回焦点を当てたいのは、
『楽しく覚える』 ということ。
受験のためとはいえ、まだ小学生ですし、せっかくなので、できるだけ印象に残るように楽しく覚えたいもの。
楽しく覚えたものは、自然と長期間の記憶を保ってくれます。 (私も大人になっても「水兵リーベ・・」とか「一夜一夜に人見ごろ」とか覚えてますもんね。)
おすすめの楽しい暗記法3選
では、具体的にどうすれば楽しく覚えられるのか?おすすめは、次の<span class=”ylw”>3つの方法</span>です。
① 語呂合わせ
語呂合わせは、定番かつ効果抜群の暗記法です。
たとえば、理科の主要な単子葉植物は、
・イネ ・トウモロコシ ・ユリ ・エノコログサ ・ツユクサ ・チューリップ ・ネギ
などが挙げられるのですが、そのまま羅列しても、なかなか覚えてくれません。
そこで、それぞれの頭文字をとって、
なんて教えると、楽しく覚えてくれます。 (全国のイトウユリちゃん、ごめんなさい)
② ストーリーを作る
理屈ではなく感情や情景で記憶に残す方法です。
たとえば、有名どころではありますが、春の星座「春の大三角」を覚えるとき、
・おとめ座:スピカ
・うしかい座:アルクトゥルス
・しし座:デネボラ
とありますが、これをU字型に読んでいくと、
なんてストーリーを強引につけてしまうと楽しく覚えてくれます(笑)
歴史マンガが人気なのも、ストーリー仕立てで知識が定着しやすいからなんですね。
③ リズムや音を取り入れる
リズムにのせて覚えるのも効果的です。
九九や英語の歌、円周率の暗唱など、リズムで記憶することで“耳”からも定着できます。
円周率を10万桁暗唱という世界記録を成し遂げた、原口さんという方も、10万桁の円周率を「語呂」「ストーリー」「リズム」で覚えていたそうです。
お子さんがノリのいい音楽でリズムに乗って覚えるのが好きなら、ぜひ取り入れてみてください。
時には お子さんと一緒に、「楽しい覚え方」を考えてみるのもいいのではないでしょうか?
お母さんも一緒に!親子で「楽しい暗記」を考える時間を
暗記に苦手意識があると、お子さんはどんどん勉強がつらくなってしまいがち。
そんなときこそ、お母さんが一緒に「楽しい覚え方」を提案してあげると、お子さんのやる気もぐっと上がります。
たとえば、
「この語呂合わせ、ママも使ってたよ」
「この歌にのせたらどうかな?」
といった親子の会話が、家庭学習を前向きにしてくれるはずです。
楽しく覚える=受験が遊びになってしまう、というわけではありません。
むしろ、楽しく学べる時間が増えるほど、効率よく知識が身につき、結果として合格への近道になるのです。
まとめ
中学受験で求められる知識は多く、暗記は避けて通れません。
大切なのは、「ただ何度も繰り返す」だけではなく、「どうすれば自分の中に定着するか」を考えること。
特にお子さんが暗記を苦手としているなら、「語呂」「ストーリー」「リズム」の3つの方法をぜひ試してみてください。
親子の会話の中から生まれる“楽しい覚え方”が、お子さんの記憶力をぐんと育ててくれますよ。
コツコツと、でもちょっと遊びごころを忘れずに!一歩ずつ、合格に近づいていきましょう。