子どもにとって「遊び」は本当に無駄なのか?
中学受験に向けて本気で取り組む家庭ほど、「遊び=悪」と捉えてしまいがちです。
塾講師という立場上、勉強第一の姿勢を強調すべきかもしれません。
ですが今回、あえて“遊び”の大切さについてお話したいと思います。
お盆休みに、私は九州に住む親戚の家を訪ねました。
そこで出会ったのは小学5年生の男の子。地方に住んでおり、中学受験は考えていません。
学校の宿題をこなす程度で、勉強は得意ではない様子。
けれど、スポーツが好きでとても元気で明るい子どもでした。
夏休み中、その子は思いきり遊び尽くしていました。
海では家族のクルーザーで海風を感じ、川では水の掛け合いをして大声で笑い、
夜にはお墓参りの後に花火で遊ぶ……そんな光景が日常でした。
そうした生活の中で、その男の子は友達も多く、人懐っこく幸せそう。
勉強は苦手かもしれないけれど、十分に子どもらしく生きているように思えました。
勉強よりも大切?子ども時代の「実体験」の価値

確かに、勉強から逃げ続ければ将来は大変なこともあるでしょう。
ですが、「遊び」を通して得られる経験は、実は将来の糧になることがあります。
私自身、子どもの頃に夢中で遊んだ思い出は、今でも心に残っています。
お金にはならないけれど、お金では決して買えない価値ある記憶です。
「勉強=将来の成功を約束する手段」だと考えるなら、
「遊び=成長過程でしか得られない資産」だとも言えるでしょう。
特に、自然と触れ合う、家族で出かける、体を使う遊びなど、
五感と心をフルに使う体験は、コミュニケーション能力や感受性の形成に役立ちます。
以下に「勉強」と「実体験を伴う遊び」の違いや価値をまとめてみました。
| 項目 | 勉強 | 実体験を伴う遊び |
|---|---|---|
| 得られるもの | 知識、思考力、基礎学力 | 社会性、表現力、感性、記憶に残る体験 |
| 時間効率 | 高め(目的が明確) | 低めだが深い学びに繋がる |
| 将来的影響 | 学歴や進路に直結 | 人間力や人生の価値観形成に影響 |
中学受験でも「メリハリ」を意識して過ごす
中学受験のためには、どうしてもある程度“遊び”を我慢しなければなりません。
しかし、すべての遊びを禁止してしまうと、心のバランスを崩す可能性もあります。
子どもたちに必要なのは、「メリハリをつけた生活」です。
何時間もダラダラとゲームやテレビを観るのは、確かに好ましくありません。
けれど、実際に体を動かして遊び、人と関わる時間は、人生の土台になるかもしれません。
過度なプレッシャーや疲労が蓄積してしまっては、
勉強の効率も下がってしまいます。
夏休みや長期の講習期間中でも、1日の中で30分でも1時間でも、
本当にリフレッシュできる時間を意識的にとってみてください。
お子さん自身が「また頑張ろう」と思えるような遊びなら、
それは決してマイナスではありません。

今回の記事のまとめ
- 遊びにも「実体験を伴う価値ある遊び」と「無駄な遊び」がある。
- 感性や社会性は、実体験の中で育つ面も大きい。
- 全ての遊びを我慢させることは、逆に成長にマイナスとなる可能性もある。
- 中学受験期の“遊び”は「メリハリ」がキーワード。
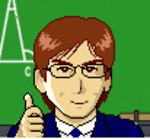
子どもの未来を考える親御さんとして、
「我が子の成長に本当に必要なことは何なのか」を、今一度考えてみませんか?




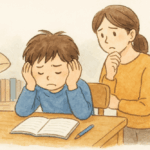

コメント
突然のコメント失礼いたします。
ブログ拝見しました。とても素晴らしいブログですね。
すごく良いブログだったので、思わずコメント
してしまいました。
また、じっくりと過去の記事なども読ませていただきます。