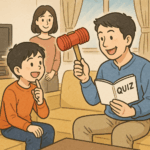宿題のわからない問題、どう対応させていますか?

「宿題中にわからない問題があったら、どうしてる?」
私は授業中にこう、生徒たちに質問することがあります。
すると返ってくるのは、
「やる気がなくなる」
「あきらめる~」
といった声。。。
この時点でちょっと心配になりますが、次に続くのは…
「解説を見る~」
「お母さんに聞く」
「先生に聞く」
決して間違いではありませんが、私はさらにこう続けて投げかけます。
「その前に、自分でやるべきことがあるんじゃない?」
しばらく沈黙してから、
「ノートを見る」
「教科書を調べる」
という言葉が出る子も。
そう、それが本当に大切なんです。
まず、「自分で調べる」こと。
これは中学受験を成功させる上で、必ずと言っていいほど必要になる大事な習慣です。
ノートやテキスト、参考書や辞書など、手元にあるリソースを使って自分で調べる力を養うことが、やがて「考える力」に直結していきます。
自分で考える子は、成績も伸びる子
お子さまに同様の質問をしてみてください。
「宿題中にわからない問題があったら、どうする?」
きっと、
「面倒だからパスする」
「時間がないから解説を読むだけ」
といった返事もあるのではないでしょうか?
「めんどくさい」 「宿題の量が多いから時間がない」
といった理由で、“自分で調べて考える”ということをしない傾向があります。
環境が整っている場合ほど、“調べる”行為をしなくなる傾向もあります。
そしてこの習慣はやがて、
…につながっていきます。
その結果、テストでも点数が取れない。
さらに進むと、自力での問題解決ができず、「カンニング」など、問題行動に発展してしまうケースも見られます。
自学自習は小5後半からが勝負!親は教えすぎないで
中学受験に向けて、本格的な“自学自習”の姿勢が必要なのは、小学5年生の後半から。
これは、多くの進学塾や教育現場でも一致している考えです。
『中学受験バイブル』の著者・荘司雅彦氏も、自著の中で「算数では教えすぎて失敗した」と述べています。
親御さんがわかりやすく教えてしまったことで、逆に子どもが考える機会を失ってしまうのです。
私も生徒への質問対応では、すぐに答えを教えることはしません。
できるかぎり
「自分でノートを見てみた?」
「その前の問題と違うところはある?」
とヒントだけ与え、自力での気づきを促します。
これは、子ども自身の“脳の成長”を信じてのアプローチです。
分からない時の対応ステップと「成功体験」の重要性
では、実際に宿題でつまずいたとき、どんな順番で対応させるべきかをまとめておきましょう。
| ステップ | 対応する内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 自分で調べる | ノート・教科書・解いた問題を見直す |
| 2 | 解説を見る | 解説書ならできるだけ自力で読ませる |
| 3 | 人に聞く(親・先生) | ヒント程度に。すぐに答えを言わない |
| 4 | 1~3でも解決しない場合は保留にして後回し | 無理に理解させず、基本に戻るのも◎ |
このプロセスを踏むことで、「自分の力で分かった!」という経験が積み重なります。
この「成功体験」こそが中学受験を頑張る子どもの最大の原動力。
自分で1つの壁を越えたという実感が、やがて自信となって積み上がっていきます。

今回の記事のまとめ
- 宿題でつまずいたとき、すぐに答えを見る前にまず「自分で調べさせる」
- 自学自習の習慣は、小5後半からが重要なタイミング
- 親が教えすぎると“考える力”が育ちにくい
- 自力で「分かった!」という体験が子どもの自信につながる
- ステップを踏んだ問題への取り組みを、親子で習慣化していこう
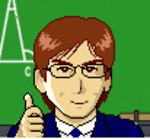
「勉強ができる子」は、「自分で考えられる子」。
その土台作りは、日々の宿題への取り組み方から始まります。
ぜひ、今日から「まず調べさせる」習慣を意識してみてくださいね。