恵まれた現代の子供たちに必要な「厳しさ」
現代は少子化の影響もあり、お子さん一人一人がとても大切に育てられている家庭が多いです。
ご家庭で手間ひまかけて作られるお弁当、整えられた勉強環境、ゲームや動画などの娯楽、日々の丁寧なコミュニケーション。
お子さんたちは本当に恵まれた環境で育っています。
だからこそ、私はあえて「適度な厳しさ」も必要だと感じています。
もちろん、子供の気持ちに寄り添い、しっかり話を聞き、認めてあげることは基本です。
しかし、子供を正しく導くためには、ただ甘やかすのではなく、時に毅然とした態度で接する「厳しさ」が大切だと思うのです。
家庭でも、夫婦間で「厳愛(げんあい)」=厳しさと、「慈愛(じあい)」=優しさのバランスを意識することが大切です。

子供は「自分を守るため」に嘘をつくもの
突然ですが、お子さんの「嘘」に戸惑った経験はありませんか?
私たちのように進学塾で日常的に子供たちと接していると、子供はたやすく嘘をつくものだという現実を目の当たりにする機会が多くあります。
もちろん、大人であっても自身の不利益を避けるために嘘をつくことはありますし、「嘘も方便」という言葉もあります。
けれども、子供たちがつく嘘は「誰かを助けるため」ではなく、「自分を守るため」のものが圧倒的に多いのです。
塾ではよく、
「宿題やったと言いつつ、実はやってない」
「答えを写しておきながら、自分で考えたように見せる」
「模試でカンニングしたのに知らんふりする」
といったケースを確認します。
このような嘘は、見逃してしまうと「バレなければ大丈夫」という価値観を植えつけてしまいます。
実際に私が経験したケースでは、カンニングをした生徒が必死で否定し、その親御さんまで「うちの子がそんなことをするわけがない」と講師に抗議し、最終的に法的手段をちらつかせる騒動にまで発展したこともありました。
嘘を追及しすぎず、上手に教えることが大切
子供が嘘をつくことはある意味、自然なことです。
しかし、その嘘をそのままにしておくと、«嘘をついて逃げる»ことが癖になってしまいます。これでは、将来の人間関係や社会での信頼を失う原因になります。
だからといって、嘘をしたことを必要以上に責めたり、真実を徹底的に追及する必要はありません。
大切なのは、
“嘘をつくことは結果として自分のためにならない”と
子供自身に気づかせるような働きかけです。
たとえば、
「もし先生やお母さんが信じてくれなくなったら、悲しくない?」
と、子供の感情に寄りそいながら優しく伝えることで、“信頼の大切さ”を理解してもらうようにしましょう。
親として、子供の「嘘をつきたくなる気持ち」も「自己防衛本能」だと受け止めつつ、
その子にとっての「善悪の基準」をじっくり育てていくことが重要なのです。

今回の記事のまとめ
- 現代の子供たちは恵まれた環境にあるからこそ「厳しさ」も必要
- 子供の嘘の多くは「自分を守るため」のもの
- 嘘を責めすぎず、嘘がもたらす影響を理解させる働きかけが大切
- 嘘を習慣にしないための「親の対応」が将来的な信頼関係の基礎となる
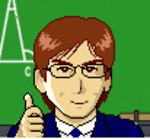
お子さんが信頼できる大人に育つためにも、「優しさ+厳しさ」の絶妙なバランスで支えてあげましょう。







コメント
ろぼりん さま
カンニングというと、ついつい目くじら立ててしまいそうですが、何だか心温まるお話、ありがとうございます。
「真相は藪の中」でも構わないんじゃないでしょうかね。
自分自身に嘘をつくことはできませんので、これを機に娘さんが成長してくれれば結果オーライです。
色んな失敗をして人は大きく成長するものですから、様々なマイナス要素も成長のためのバネにしていきたいですね。
素敵なコメントありがとうございました。
いつも先生のブログ、楽しみに読ませていただいております。
さて、カンニングのお話。
現在中1の娘もやってくれました!(笑)
その場で行為を見とがめられ、「帰れ!」と怒鳴られ帰宅した娘・・。
授業中にもかかわらず、「いいわけも聞いてやることなく帰してしまいました・・・。」と電話をくださった先生。
先生の電話が娘の帰宅よりも早かったので、私も心の準備ができ、落ち着いて娘の話を聞くことができました。
成績は振るわないけれど、要領は悪いけれど、正直で優しい娘・・、カンニングなんてするわけが・・・・・!というのが親心でしたが、プロである先生の目からみれば明らかだったようでした。当日、深夜の塾に行き先生と話をさせていただき、「今回は僕の勘違いだったことにしておきましょう。来づらくなってはかわいそうですし・・。」ということで落ち着きましたが、未だ真相は藪の中です。
娘のことも先生のことも大好きな私は結局、娘には「先生が謝ってくださったわよ。」と言い、先生には「悪者にしてしまって本当に申し訳ありません・・。これからもよろしくお願いします。」
と頭を下げました。
しこりを残さずに済んだのは日頃から信頼関係を築いておけたからかな、と今改めて思います。