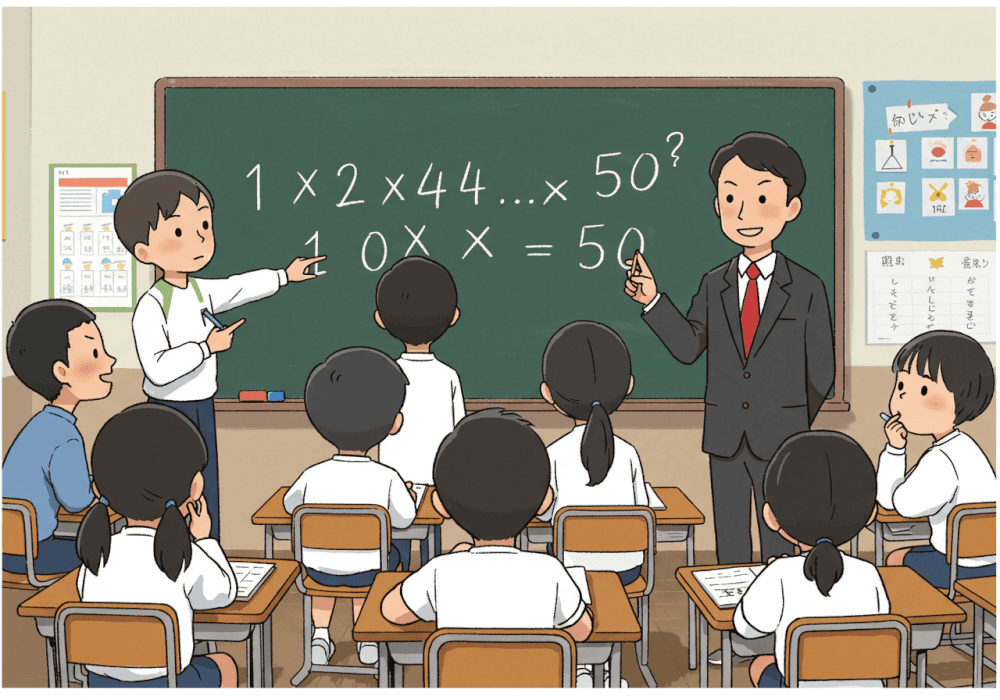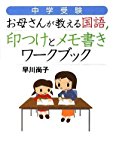子どもの「分からない」を放っておかないで
中学受験を目指す小学生の親御さんへ——。
お子さんが塾から帰ってきて、「今日はぜんぜん分からなかった…」とため息をついた経験、ありませんか?
これは、放っておかずに向き合う大事な瞬間です!
今回は、算数の授業で実際にあった出来事をご紹介しながら、お子さんの「思考力」と「本当の理解力」を育てるにはどうしたらいいのかを考えてみましょう。
ある日の5年生の授業で、私は冒頭に次の問題を出題しました。
問題:1×2×3×4×…×50 の計算結果の末尾に 0 はいくつ並ぶ?
すでに夏期講習で軽く触れた問題だったので、少しは覚えているかな、と期待して出題したのですが…。
ほとんどの子どもたちがすっかりやり方を忘れてしまっていました。
「素因数分解…とかしたっけ?」と、おぼろげな記憶を頼りに悩む子。
なかには計算パターンを無視して、根性で1つずつ筆算している子も……。
結局、5分経っても誰も正解にたどり着けず、授業を中断することに。
さて、皆さんはこの問題、どう解くか分かりますか?
たった8秒で解ける問題とは?
私は黒板の前に立ち、ストップウォッチをスタートさせました。
以下の計算式を示すと:
“`
5 )50
5 )10
2
10 + 2 = 12
“`
そう。正解は「12個の0が並ぶ」です。
これは「50!」の中にいくつ『5』が含まれているかを数える問題。
10は「5 × 2」からできるので、『5』の数を調べれば末尾の0の数が分かるんですね。
50÷5で10個、さらにその10÷5で2個。
これらを足して「12」。
この計算、解き方さえ分かっていればたった8秒です。
生徒たちが根性で書き殴った10ページ分の筆算が、まるで幻のように感じられたことでしょう(笑)。
「えっ、そんな簡単なの?」
「さっきの苦労は何だったの…?」
と、生徒たちは驚きの声をあげていました。
苦労してからこそ、定着する学び
でも、実はこれで良いのです。
なぜなら、「自分の頭で一度考えて苦しんだ経験」があるからこそ、簡単な解法の意味が深く理解できるんです。
私はこのタイミングを見計らって、改めて数論の基本に立ち返り、同様の問題を分かりやすく解説しました。
すると、その後の授業では、生徒たちは誇らしげに似た問題をスラスラ解けるようになっていたのです。
この「苦労する経験」こそが、記憶と理解を深くする鍵です。
逆に言えば、「最初から正解を教えられてばかり」では、本当の理解にはつながりません。

美しい解法より、まずは自力でぶつかってみる
日本トップクラスの進学校、灘中学・灘高校では、数学の授業で「誰の解法が一番美しいか」を競いあうという話もあります。
けれど、そこに至るまでには、自分なりに考え抜き、失敗を繰り返す過程が必ずあります。
参考書や動画で「きれいな解法」を丸暗記するだけでは、応用力は育ちません。
大切なのは、お子さんが「自分の力で考える時間」をしっかり持つこと。
ときには間違えたり、苦しんだりしながらも、「あっ、分かった!」と自分で解決できる経験が、最大の学びにつながります。
家庭でのフォローとしては、すぐに答えや解き方を教えるのではなく、
「これって何が問われているのかな?」
「どうやって10ってできるのかな?」
といった「気づき」のヒントだけを投げかけてみてください。
お子さんの思考力を引き出し、自信につながるはずです。
まとめ:完璧な解き方より、自分で道を切り開く経験を
中学受験算数は、単なる計算力ではなく「探究力」と「柔軟な思考力」を問われる教科です。
計算ミスをしないように練習することも大切ですが、最も重要なのは「自分の頭で考えようとする姿勢」。
最初は根性での「筆算地獄」でも大丈夫!
その中でしか気づけないこと、そこからしか見えない世界があります。
ぜひ、お母さんの温かいサポートで、「間違えても、分からなくても大丈夫」という安心感をお子さんに届けてあげてくださいね。
それが、算数だけでなく、これからの学びすべてに通じる「強さ」となるはずです。