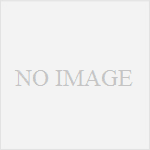「くもん、行くもん!」で有名な公文式とは?

「くもん、行くもん!」という印象的なCMでもおなじみの公文式学習法。教育に関心のある保護者の方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
私自身は実際に公文で学習したり、指導した経験はないのですが、大学時代に教育の勉強をしていた際、「公文式」という学習法に出会い、大きな衝撃を受けたことを今でも覚えています。
公文式の一番の特長は、「完全個別定着のレベルアップ方式」を採用している点です。
つまり、一人ひとりに合わせてカリキュラムを進めていけるため、集団授業のように「ついていけない子」や「簡単すぎて退屈する子」が出にくい学習スタイルになっているのです。
子どもの理解度に応じてステップアップしていけるので、学習に対する達成感も得やすく、習慣化もしやすいという大きなメリットがあります。
たとえば、苦手な子は基礎からじっくり、自分のペースで取り組めますし、得意な子はどんどん先へ進め、小学生で中学生レベルの内容(連立方程式など)を学んでいるお子さんもいるほどです。
このように、それぞれの子どもに合わせた無理のないステップアップができるという点で、公文式は非常に優れた学習法といえます。
公文式で培った力は中学受験にどう活かせる?
私のように中学受験専門の進学塾で指導をしていると、公文経験者のお子さんと出会うことも少なくありません。
このようなお子さんに共通しているのが、「計算力が高い」や「計算スピードが速い」という点です。
この点は、中学受験の算数において非常に大きなアドバンテージになります。受験算数でも、基本的な計算処理は欠かせないので、公文式で身に付いた力が活きてくるのは確かです。
ただ、一方で注意したいポイントもあります。
公文式では基本的に「計算分野」に特化しているため、いわゆる中学受験で必要とされる「文章題」や「図形問題」に必要な読解力・論理的思考力などは訓練されていません。
そのため、受験算数に求められる「文章を丁寧に読む力」や「試行錯誤して考える力」は、公文だけでは身につきにくいのです。
特に、公文経験のあるお子さんの中には「計算はすごく得意なのに、文章問題になると急に手が止まってしまう」というケースがよくあります。
計算力がある=算数が得意、と思っていたお子さんにとっては、非計算系の問題に直面したときに「こんなはずじゃなかった…」と落ち込んでしまうことも。
それでも、計算力は「土台」の部分。中学受験に向けて、しっかりと戦える基礎を築いていることは間違いありません。
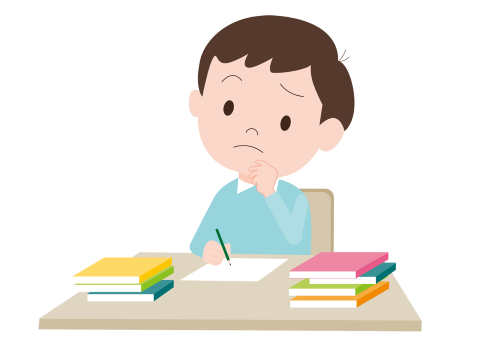
公文から受験勉強へ、効果的な移行タイミングとは?
そうなると、気になるのは「いつ受験勉強に切り替えるべきか?」という点だと思います。
結論から申し上げると、「小4から本格的に中学受験対策を始める」のであれば、それまでに公文式で基礎力(特に計算力)を固めておくのはとても効果的です。
小学校低学年までは、無理に応用的なことを求めるよりも、確実な基礎習得を重視すべき時期です。
このタイミングで公文式のような、反復練習によって力を積み重ねていく学習法を取り入れるのは理にかなっています。
ただし、小4以降は中学受験用の専門的な内容を学び始める必要があります。
この段階では「文章読解力」、「論理的思考力」、「試行錯誤を楽しむ力」といった、より高度な力を育てていく必要があります。
このタイミングで、進学塾に移行したり、適切な学習教材を使用しながら、徐々に新しい学び方に慣れていくことが重要になります。
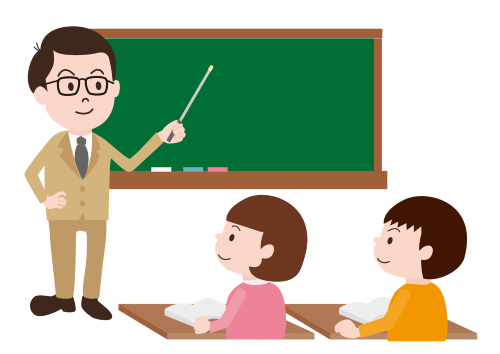
今回の記事のまとめ
- 公文式は完全個別型のステップ学習法で、基礎の定着に強みあり
- 計算力とスピードの向上は、中学受験の土台作りとして非常に有効
- 文章題や図形問題には特化していないため、受験対策には別途トレーニングが必要
- 小4以降の受験勉強に備えて、低学年時に公文で基礎固めをするのは効果的な選択
公文と中学受験の違いをしっかり理解し、無理のない形でスムーズに受験学習へ移行することが、お子様の学習成功への第一歩です。