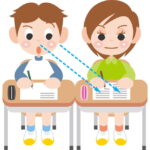成績がなかなか伸びない時に感じる焦りと不安
――「教育は忍耐である」――
これは、私がどこかで聞いてずっと心に残っている言葉です。
塾講師として長年教えてきた中で、指導のたびに思い出すようになったこの一言。
私たち講師は、授業を計画する際、「このレベルまで理解してほしい」と理想を持って指導しています。
しかし、実際は思うように成果が出なかったり、生徒の理解が追いつかなかったりすることも多いのが現実です。
ある単元が難しいのか、生徒の相性によるものか、あるいは教科の得手不得手が関係しているのか…。
同じように教えても、昔の生徒と比べて今の子の理解に差を感じることもあります。
全員が真っ直ぐに伸びていくわけではありません。
補習に呼んで手をかけても、成績の上がらない子は確かにいます。
逆に、まるで背中に羽が生えているかのように放っておいても自分で伸びていく子もいます。
そうなると、講師としても当然悩み、時に落ち込むこともあります。
親御さんの“理想”が子どもの成長を妨げることも
ある日、成績が思うように伸びないお子さんをもつお母さんから電話をいただきました。
話を聞くうちに、私はそのお母さんが本当に一生懸命であることが伝わってきました。
お子さんの勉強を手伝い、一生懸命向き合っている。
しかし成績は思ったように上がらない。
きっと、お子さんの地頭や性格による部分もあるのでしょう。
しかし、それ以上に気になったのが、お母さんの中にある「理想の高さ」でした。
良くなってほしいと願う一心で、できない部分ばかりが目についてしまう。
これはどのご家庭でも起こりうることです。
理想と現実のギャップに悩むうちに、お子さんへの不満が募り、次第に講師への不信感さえ芽生えてしまうこともあります。
そして、そこから始まる「負の連鎖」。
お母さんの焦りやイライラは、少なからずお子さんにも伝わり、それがまた勉強へのプレッシャーへとつながってしまいます。
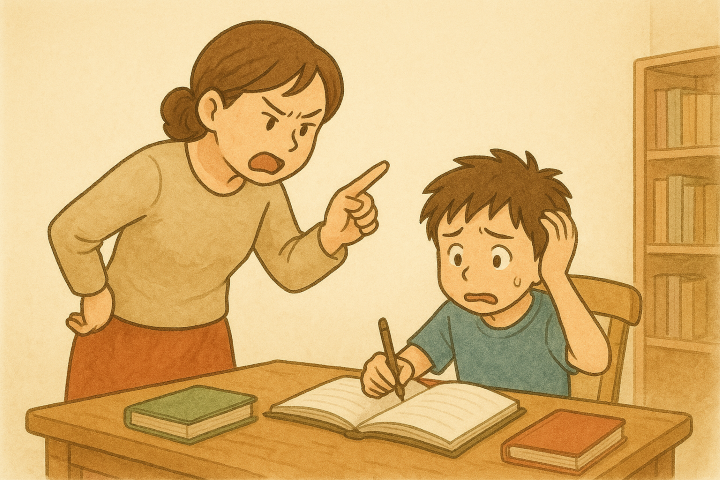
このようなとき、親御さんにはぜひ知っておいてほしいのです。
勉強には「時間と積み重ね」が必要であると同時に、愛情と認める気持ちも欠かせないのだということを。
お子さんの成長を見るのは“絶対評価”で
私たち講師も、成績が上がらないときは毎回立ち止まり、分析や対応を試みます。
レベルを下げて、何が原因かを一緒に考える時間も取ります。
保護者の方と同じように、講師にとっても「成績が伸びないこと」はとてもつらいことです。
でも、そこで大切なのは「冷静さ」と「忍耐」。
テストの点数や成績の変動だけに一喜一憂するのではなく、
お子さん自身の“中身”の成長に注目してあげることが最も重要なのです。
成績は相対評価――つまり、周囲と比較されてしまうもの。
周りの子の伸び方によって、見かけ上成績が下がったように見えてしまうこともあります。
だからこそ、親として接する時は「絶対評価」で見てあげてください。
昨日より少しでも前に進んでいるか、努力しているか、解ける問題が一つでも増えたか。
その「小さな成長」を必ず見逃さず、認めてあげることが、お子さんの自信と前向きな気持ちにつながります。
今回の記事のまとめ
- 子どもの成績は簡単には伸びません。教育には“忍耐”が必要です
- 親の理想が高すぎると、子どもへのプレッシャーが成績低下につながることもあります
- 子どもの努力や成果は、相対評価ではなく“絶対評価”で見てあげることが大切です
- 成長の「小さな変化」に気づき、褒め、認め、励ますことが、次の一歩につながります
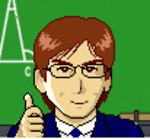
――「教育は忍耐である」
今一度この言葉を胸に、子どもの可能性を信じて、温かく見守っていきましょう。親御さんの笑顔は、お子さんにとって最高の励ましだと思います。