理科の知識がなかなか定着しないお子さんへ
小学校6年生の理科を担当している中で、多くのお子さんがつまずくのが「暗記量の多さ」です。
中学受験の理科は、単なる理解だけでなく、圧倒的な知識の蓄積が求められます。
塾では「授業で学ぶ ⇒ 家庭で復習 ⇒ 授業で確認テスト」というサイクルを繰り返していますが、テスト結果が思わしくない子も少なくありません。
ですが、お子さんたちは非常に前向きです。
「もう一回やって覚えるので、同じテストをください!」と自ら申し出る子も多く、その姿勢は成長につながります。
とはいえ、何度も繰り返しているのに覚えられないときには、勉強方法を少し工夫する必要があります。
そこでおすすめなのが、「耳から覚える」学習法です。
耳から聞いて覚える力を引き出そう

赤ちゃんや幼児が言葉を覚える過程は、「耳から聞いて」が基本です。
たとえば、言葉を話せるようになる過程や、外国語を自然と身につけるのも、耳からの刺激によるものです。
これは大人や小学生にも応用できる方法で、脳科学的にも有効です。
記憶を担当する「海馬」には、目からの情報と耳からの情報、それぞれ異なる神経経路を通って情報が届きます。
つまり、テキストを読んでも覚えられない場合でも、音声で聞くことで記憶に残る可能性があるのです。
苦手意識のあるお子さんほど、視覚だけに頼らず聴覚を使って、「別のルートから脳に届ける」工夫が有効です。
歌や音読、録音活用で「覚える」を楽しく
音楽の歌詞を自然と覚えてしまうように、理科や社会の知識も「リズム」や「メロディ」に乗せると、記憶への定着が格段に上がります。
最近は中学受験向けの“覚え歌CD”や、理科・社会をテーマにした音声教材が市販されており、評判も上々です。
通学途中や寝る前など、スキマ時間に聞き流すだけでも効果的。
また、お子さん自身の声で教科書の内容を録音し、それを聞き返すだけでも大変いいトレーニングになります。
自分の声でインプットすると、「話す」→「聞く」→「思い出す」という複数の脳の使い方がされ、記憶が深まります。
おすすめは以下の方法です。
– 用語集や語句をお子さんが音読して録音
– スマホやICレコーダーで簡単に録音可能
– 通学中や寝る前などに聞き流す習慣づけをする
– 音声教材や歌CDを併用
これにより、理科の「用語→意味」の関係性が自然に頭に入るようになります。
目と耳を両方使って、脳を活性化させよう
視覚的な学習と、聴覚を使った学習。この2つをバランスよく取り入れることで、お子さんの脳の働きがより活発になります。
特に小学生のうちは、脳が非常に柔らかく、吸収力が高い「ゴールデンエイジ」です。
ここで様々な入力方法を経験させることで、記憶力だけでなく集中力や理解力の向上も期待できます。
中学受験はゴールではなく、今後の学びの土台となる大切なステップです。
「覚えられない=能力がない」ではなく、「覚える工夫」が足りないだけかもしれません。
ぜひご家庭でも、「耳から覚える」習慣を取り入れてあげてください。
お母さんの声で録音してあげるのも、子どもにとっては安心感があって良いかもしれませんね。
少しの工夫が、結果に大きな変化をもたらしますよ。






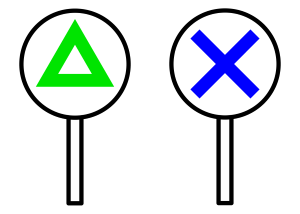
コメント
ありがとうございます。
最近は退学や外部受験されるお子さんが増えているようです。
私立中学受験はリスクが大きいなぁーとつくづく感じています。
偉そうなことが言える立場ではありませんが、親の役目は有名大学に入れることがメインではないと思いますよ。
お子さんが元気に前向きに成長できるよう、ぜひ応援してあげてくださいませ。
ありがとうございます。
新興校のような雰囲気は嫌いなのですが…
でも55~60の偏差値になると自由で闊達な学校は望めないのが現実です。
希望しない学校で6年間もその学校のカラーに染まってしまう恐ろしさはありますが子供は水者…高校受験にモチベーションが高まるかわかりません。
私立中学はどこの学校が好きだとか言っても所詮合格を頂けた学校へしか進めない…二月は乱射撃のように行かないと一月受験の学校しか残らなかった~なんて悲惨な場面が押し寄せる。
公立へ戻しリベンジさせたい思いはあれど子供の三年後までのモチベーションの維持は⁈予測不可能。
だから家庭教師の力を借りてでも附属に入れれば親の役目は終了にできるんですよ。
考えてもどうにもならないので子供に任せます。
お子さんの状況に応じていずれの選択もあり得ると思います。
もちろんご家庭の相談の上での方針が一番ですが、早熟でないお子さんの場合は有名附属校なんかはオススメはしませんね。
エスカレーター式の大学附属校は、倍率も高くて厳しい受験になりますし、更に入ってからは間違いなく勉強しなくなりますので(笑)
ダメ学生をたくさん生み出してしまう(笑)偏差値の高い附属校よりも、面倒見良く育ててくれる偏差値が低めの進学校の方がゆくゆくは本人の選択肢も増えてきますし。
それなのに、やっぱり附属校が人気なんですよねぇ…
もちろん高校受験の道もあります。
高校受験も早いうちから取り組んでいたほうがもちろん有利にはなります。
私立高校などは、中学受験の学習をしていたほうが圧倒的に有利にはなります。
本人の意向もあると思いますので、ご家族と相談の上、柔軟に対応していかれるとよろしいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
本人が受験塾へ通うことが楽しく学習が好きではあれば続け程々の所で大学受験を考えることがよいのでしょうか。
(そうなると六年間通わせる学校を考えてしまいます。)
それとも中学受験塾通いは辞め英語学習に向けることが高校受験へのモチベーション向上につながるのでしょうか?
やはり受験を最後まで走るとそれなりにダメージや失望もありますよね。
大切なのはどう生きるか…
辞書では、『すぐれた知恵。深く物事の道理に通じる才知。』とありますが…
それは直接その講師に聞いてみるのが一番かと。
中学受験はどうしても早熟な子が有利となります。
学習訓練と割り切れば、中学受験の学習が後のお子さんの学習にも大きくバックアップしてくれますが、
何としても中学受験で大きな成果を出さないと、と力を入れすぎると、おっとりしたお子さんにとっては勉強自体が大きな負担に感じてしまうかもしれませんね。
Nの算数講師から息子の宿題ノートに「叡智」と記されてました。
これは何の意味があるのでしょうか?
息子はおっとりしていて中学受験より高校受験が合うように感じます。