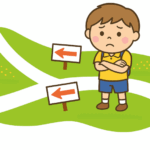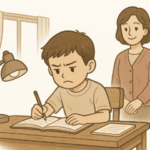日常の習慣が人生を形づくる基本になる

私たちの日常には、当たり前のように行っている習慣がたくさんあります。
でも、それらの「当たり前」も、最初から自然にできたわけではありません。
例えば、食事の後に歯を磨くこと。
大人なら当たり前のようにしていますが、子どもには教えなければ分かりません。
以前、あるニュースで、長い間施設で育った子どもが「歯磨きをしたことがない」と話しているのを見て、衝撃を受けたことがあります。
私たちにとっての常識も、誰かが教え、見本を見せ、繰り返して習慣づけた結果なのです。
また、トイレで「うんち」をした後におしりを拭く。
これも言うまでもなく当たり前のことですが、小さい頃から教えなければ身につかない行動の一つです。
おしりを拭くのと同様に、「自分でできるようになること」は、日々繰り返し教え、子どもに身につけさせる必要があります。
そしてこれは、勉強の習慣にもまったく同じことが言えるのです。
勉強習慣も「当たり前」の一つとして定着させよう

勉強も、「この時間には宿題をする」「テストが返ってきたらすぐにミス直しをする」など、ルールを習慣化すれば決して難しいものではありません。
つまり、歯磨きやおしり拭きと同じように、考える前に体が動く「ルーティン」にしてしまえばいいのです。
「勉強するのがしんどい」「ミスを直すのが面倒くさい」
最初のうちは子どもがそう感じるのも当然です。
でも、大切なのは「これをやるのが当たり前」と自然と思えるようにすること。
そうなるまで、とにかく繰り返し、家庭でも塾でも同じ行動を定着させていく必要があります。
この「勉強のルール化」が早くできる子ほど、中学受験の勉強をスムーズに進めていくことができます。
人間は3週間ほど継続すると、習慣化すると言われています。
最初は大人が声をかけ、行動を導き、やるべきことが見えてきたら自分で進められるように促しましょう。
親の声かけで「当たり前の基準」が育つ
家庭の中での「声かけ」や「習慣づけ」は、中学受験の勉強において非常に重要な役割を果たします。
「宿題を終えてからゲームね」
「ミス直しをしてからテレビね」
こうしたメリハリをつけたルールを、毎日の生活に落とし込むことで、子どもは無理なく学ぶ姿勢を身につけていきます。
特にミス直しの習慣は、学力を伸ばす上でとても大切です。
正解にたどり着くことよりも、どこで間違えたかを把握し、次に活かす力が試験では問われます。
親がしっかりこのルールを意識し、子どもと話をしながら日々の中に取り入れていくことで、勉強への抵抗感が薄れ、やがて「やるのが当たり前」になっていきます。
一見すると些細なことでも、続けていくことで大きな差がつきます。
だからこそ、今から「当たり前の基準」を高めていく声かけが大切です。
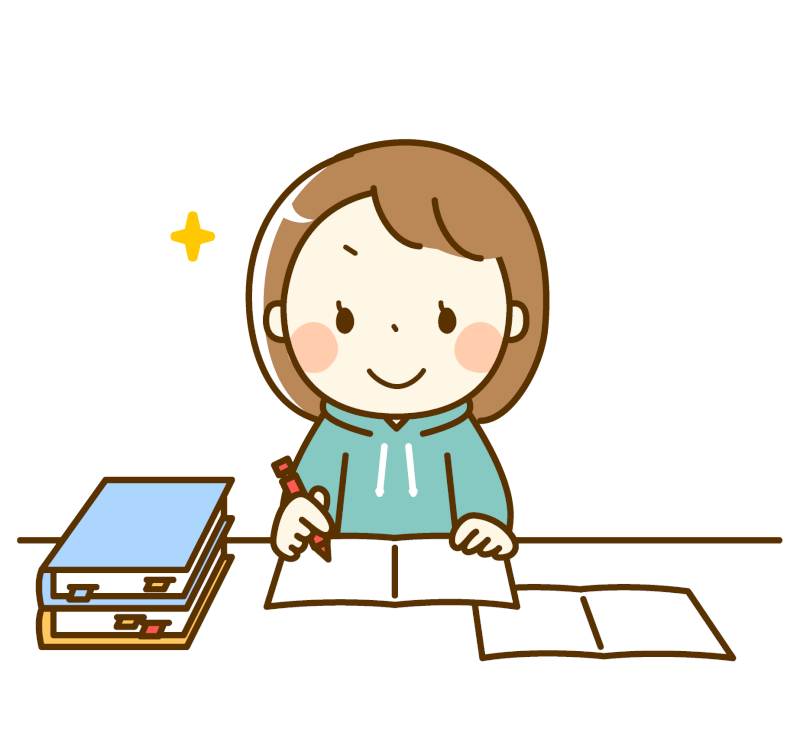
今回の記事のまとめ
- 歯磨きやトイレの習慣のように、勉強も小さな積み重ねが大切
- 「宿題をする」「ミス直しをする」は当たり前の行動として定着させる
- 親の声かけ次第で、子どもの行動は大きく変わる
- 習慣化すれば、勉強は苦にならなくなり成績アップにもつながる
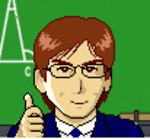
日常生活と同じように、「勉強するのが当たり前」の空気を家庭からつくっていきましょう。