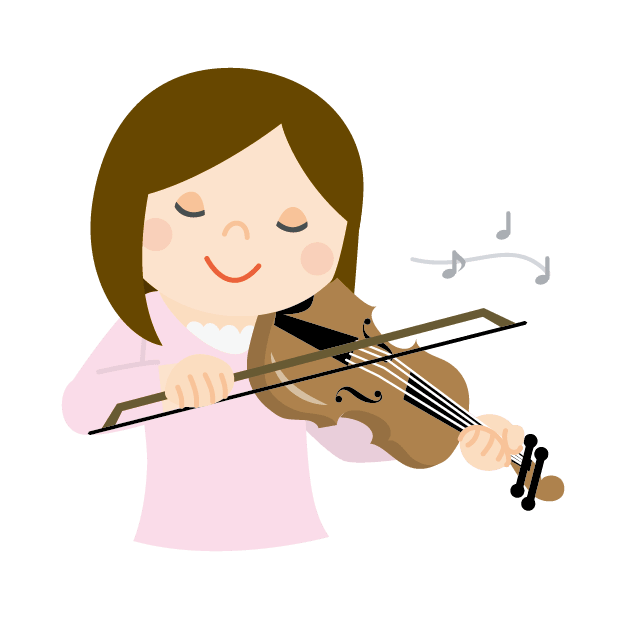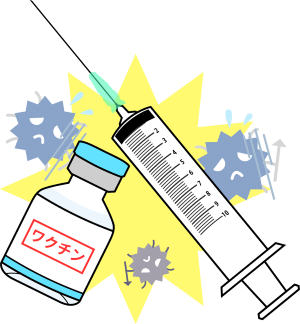登塾拒否の出来事とその背景
今回は、私が進学塾講師として経験したある印象的なケースをご紹介します。
それは、塾でもトップクラスにいたある男の子“S君”の登塾拒否についての話です。
S君は非常に賢く、地頭の良さが光るタイプ。
性格は控えめで真面目、おとなしく、大人びた雰囲気すら感じさせる子でした。
ただ、少し打たれ弱い一面もあり、典型的な繊細タイプとも言えるでしょう。
最上位クラスに所属し、有名大学附属中を志望していました。
講師陣の間でも「合格は間違いない」とすら言われていた存在でした。
しかし、そんな順風満帆だったS君に突然の転機が訪れたのです。
6年生の冬、いよいよ受験本番が目前に迫る時期になって、突然
「もう塾に行きたくない」と言い出し、登塾を拒否するようになったのです。
自宅では、塾に行く前になるとお母さんと言い争いに。
「行きなさい」「行きたくない」と玄関先で揉めながら、何とか連れていける日もあれば、頑として行こうとしない日もありました。
こうして始まった登塾拒否の状態が、1~2か月続いてしまったのです。

原因は“わずかな変化”と“受験の重圧”
もちろん、塾としても放置できる状態ではありません。
来塾した時には個別呼び出しをし、必死に本人と話を重ね、前向きになるようにサポートしました。
保護者とも頻繁に面談を行い、連携をとって対応を続けた結果、何とか冬期講習から再び塾に通えるようになりました。
結果的には、第一志望校こそ不合格となってしまいましたが、第二志望校には特待生として合格。
最後までよく頑張り抜いてくれました。
では、なぜとても優秀だったS君が、受験直前に登塾拒否に陥ってしまったのでしょうか?
大きな要因の一つは、「国語の担当講師が変わったこと」でした。
秋以降、熱血指導で保護者からも絶大な信頼を持つベテラン講師が担当するようになりました。
その講師からS君が直接叱られたことがあったわけではなかったようですが、S君にとってはなにか合わなかったのかもしれません。
ただ、それが原因のすべてではないでしょう。
中学受験という大きな目標には、塾の環境や先生だけでなく、周囲の期待や自分自身の理想が大きくのしかかります。
たった12歳の子どもにとって、想像を超えるプレッシャーを感じていたのかもしれません。
子どもが見せた小さなSOSのサイン
お母さんから聞いた言葉で、今でも心に残っているものがあります。
それはS君自身が話していた、こんな一言です。
「受験は、ポケモンと同じで、先生がトレーナーで、僕たちはポケモンなんだ」
彼の中では、受験は大人の都合に合わせて“戦わされているもの”のように映っていたのかもしれません。
この言葉には、大人が何気なく与えるプレッシャーや期待が、
子どもの内面でどのように受け止められているのかを深く考えさせられました。
中学受験を前向きに“自分事”として捉えられる小学生は、本当に一握りです。
多くの子どもたちは、不安や葛藤を抱えながら、それでも一生懸命がんばっています。
だからこそ保護者の皆さんには、目の前の成績や志望校の合否だけでなく、
その子の心の変化にも丁寧に耳を傾けていただけたらと思います。
登塾拒否にどう向き合うか:親としてできること
中学受験には、「順風満帆」などという言葉はほとんど当てはまりません。
誰もが右往左往しますし、トラブルや苦しい時期を経験します。
登塾拒否や落ち込みなども、そのごく一例に過ぎません。
それでも、その壁をどう乗り越えるかが、親子にとっても子どもにとっても本当に大切な財産になります。
まずは、子どもへの「共感」と「安心」を大切にしてください。
「行きたくない」には、必ず理由があります。
責める前に、その気持ちに寄り添い、何がしんどいのか一緒に考えてあげることこそが、親としてできる一番のサポートです。
最後に…
S君はその後、元気に中学校生活をスタートさせ、
お母さん曰く「のびのびと生活している」とのこと。
その晴れやかな笑顔が、今でも忘れられません。
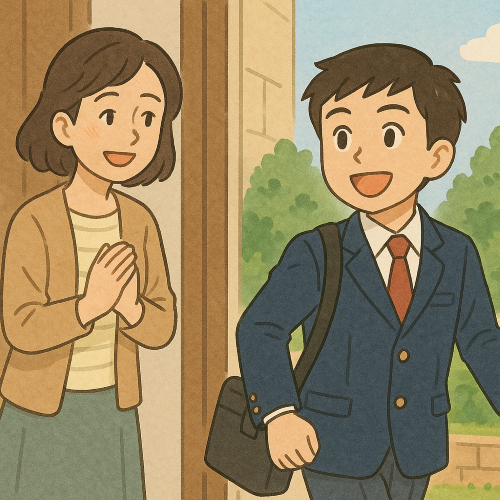
今回の記事のまとめ
- 優秀でも突然「塾に行きたくない」となることは実際にある
- 子どもに合わない講師や環境の変化がきっかけになることも
- 子どもは「がんばってるつもり」でも限界を迎えてしまうことがある
- 親は子どものSOSを見逃さず、共感と対話を大切にすることがカギ
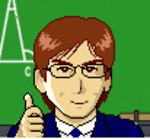
中学受験は、家族みんなで乗り越える“チーム戦”です。
転んでしまった時こそ、寄り添う温もりを大切にしてあげてください。