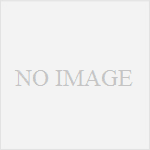根気力を育てるための時間管理と早朝学習のすすめ
中学受験に挑む上で欠かせないのが、持続的に勉強に取り組める「根気力」です。
集中力の維持には、時間の使い方に工夫が必要です。
一般的に人間が集中力を保てる時間は約90分が限度と言われています。
そのため、勉強時間は90分や60分といった単位で区切るのが効果的です。
特におすすめなのが、タイマーを利用した勉強法です。
「30分+5分休憩」など、短時間で集中しながら少しずつ持続時間を延ばしていける点が魅力です。
また、意図的に「中途半端な状態」でやめることで、次の勉強再開時にスムーズに集中に入れるという心理学的な効果もあります。
これは『ツァイガルニク効果』とも呼ばれ、記憶保持にも良い影響を与えるとされています。
勉強に取り組む時間帯にも注目しましょう。
特に効果的と言われているのが「早朝学習」です。
早朝は静かで集中しやすい環境が整っており、脳もリフレッシュされた状態です。
ある小説家の方は、集中して執筆するために毎朝4時に起きて作業をしているそうです。
もちろん夜型のお子さんもいますが、小学生は日中学校に通う生活リズムがあるため、夜遅くまで頑張るのは体力的に難しいですし、成長に良い影響があるとは思えません。
実際、ある小6のお母さんも「受験当日を想定して、今から朝型に慣れさせている」と話しており、これは非常に賢い取り組みです。
まずは朝の15分、朝食前に計算問題を解くなど、少しずつ習慣づけてみましょう。
一点集中力を高める環境づくりと「集中儀式」
学習に必要なのは「一点集中力」。
これは「目の前の一つのことに意識を集中させる力」のことです。
この力を育てるには、まず環境を整えることが第一歩です。
机の上に漫画やゲーム、スマホがあると、ついそちらに気を取られてしまいますよね。
勉強に必要のないものはすべて見えない場所にしまいましょう。
例えば、あるご家庭では、テレビを受験まで完全に押し入れにしまったそうです。
家族全員が一丸となって協力する姿は、まさに本気の証です。
机の配置も工夫をしましょう。
壁に向かって余計なものが視界に入らないようにし、次の目標や応援メッセージを貼るのもおすすめです。
たとえば
– 「絶対〇〇中に合格するぞ!」
– 「次の模試で偏差値○○アップ!」
といったポジティブな言葉は、やる気にもつながります。

また、集中力を高める「集中儀式」を生活に取り入れることも効果的です。
心理学的にも「レディネス」という言葉があり、学習するための心の姿勢づくりの大切さを説いています。
私の授業でも、授業前の挨拶を「頭の中を算数に切りかえて!」と言ってしっかり挨拶をします。
すると、ざわついていた生徒たちは気持ちを切り替えます。そして、すかさず計算テストを始めます。
スポーツでもありますが、例えば大リーグ野球選手のイチローはバッターボックスに立つとき決まったポーズを取ります。 (野球好きのお父さんはご存知ですよね)
そのポーズによって目の焦点などを定めつつ、集中力を高めているわけです。
また、イチローは野球場に入る際、必ず左足からグラウンドに入るそうです。(本人いわく、そうしないと調子が悪いのだとか・・)
これは子どもたちにも応用できます。
あくまで例ですが、以下のような「集中スイッチ」となる行動を持たせてみてはいかがでしょうか。
| 子ども向け・集中する前の行動例(集中儀式) |
|---|
| 目薬をさす |
| 好きな音楽を5分だけ聴く |
| お茶を飲んでリラックス |
| 氷を一粒食べる |
| 好きな香り(アロマやスプレー)を部屋に取り入れる |
| 1分間「何も考えない時間」を持つ |
このような儀式を習慣化し、「勉強モードのスイッチ」を体に染み込ませることが集中力アップにつながります。独自の集中儀式を持っていると、なんかかっこいいですよね。
また、勉強が苦手な子ほど、最初は「好きな教科」から始めるとスムーズです。
成功体験を積み重ねることで徐々にほかの教科にも集中できるようになります。
今回の記事のまとめ
- 子どもの集中力は「時間管理」と「学習習慣」で伸ばせる
- 90分の勉強+短い休憩が集中を継続させるコツ
- 早朝学習は頭も冴えて、根気力アップに最適
- 勉強環境を徹底的に整えることで一点集中力が高まる
- 集中のスイッチとなる「集中儀式」を決めると習慣化が加速する
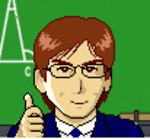
集中力は才能ではなく「伸ばすことができる力」です。
毎日の積み重ねが、自信となり、最後には大きな成果につながっていきます。
お子さんと一緒に、まずはできるところから少しずつ始めてみてください。