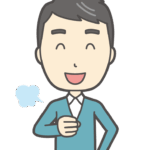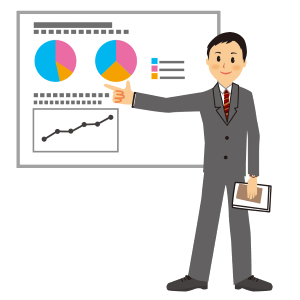親の願いが先行しすぎてしまうことがある
この記事は、あるテレビ番組「サイエンスミステリー」で放送された親子のドキュメンタリーをもとに、私たち中学受験に関わる家庭にとって非常に大切な「親と子の思いのすれ違い」について考えるきっかけになる内容です。
アメリカのある母親は、自らシングルマザーになることを決意し、「優れた遺伝子」が提供されると謳われていた精子バンクから、科学者の精子を選んで出産をしました。
彼女の目的は「天才児を育てること」。
容姿も良く、スポーツ万能、高いIQを備えた理想的なドナーを選んだのです。
生まれた男の子は非常に賢く、可愛らしい見た目や早熟な読書力により注目を集め、難関小学校にも合格。メディアに取り上げられ、「天才児」としてもてはやされるようになりました。
母親はその姿に満足し、喜びを隠せませんでした。
その後も彼は難関中学、難関高校、そして優秀なIQ180の青年へと成長。特に数学に強く、誰もが羨むエリートコースを歩んでいたのです。
エリートでは得られなかった「本当の幸せ」
しかし、番組の後半で描かれた24歳の現在の様子は、母親が夢見ていた未来とはどこか違っていました。
彼は現在、小学校2年生の担任教師として働いています。
彼の部屋には本がたくさん並んでいますが、そこには数学の本ではなく、ファンタジーや絵本の姿が目立ちます。
昔とは違い、今の彼は穏やかで自然体。
充実した表情で教え子たちについて語っていました。
しかし、インタビュー中に「才能」や「IQ」について話が及ぶと、彼の表情は一変し、暗くなります。
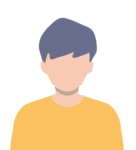
IQが高ければそれで幸せというわけじゃない。IQは素質の一部にすぎない
と彼は語ります。
周囲から特別な存在として見られ、「天才」と称されながら育った彼は、いつしか内向的になり、周囲との関係が希薄になっていきました。
孤独を感じていた少女のように、幼い頃から「普通」や「平凡」を夢見るようになります。
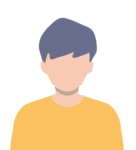
母は今でも過度なものを僕に求めてくるんだ。
だけど、僕はシンプルな人生に惹かれる
彼が今集めている本は、幼い頃に読んだ思い出の絵本。
「家族が仲睦まじく暮らすアヒルの物語」。
彼はその日常に幸福を感じ、将来もし自分に子供ができたら読み聞かせたいと語ります。
中学受験における「親の夢」と「子供の人生」
中学受験に取り組む家庭でありがちなのは、親御さんが「より良い進学先」や「将来の安定した人生」を思い描きすぎてしまい、その軸に子供自身の気持ちを置き忘れてしまうことです。
もちろん、親の期待が悪いわけではありません。それは愛情からくるものですし、子どもに良い環境で育ってほしいという健全な思いであることは間違いありません。
しかし、注意すべきなのは「その期待が子供の幸福そのものと同じものである」と思い込んでしまうことです。
親の願いが、いつの間にか「子の人生」を縛ってしまっていないか。
親の理想と子供の現実の中にギャップがないか。
一度立ち止まって見つめ直すことも必要です。
塾講師として15年以上、数多くの親子を見てきた中で、成績が良くても心がすり減ってしまった子供や、勉強は得意ではないけれど、自己肯定感を持って成長していける子供の姿をたくさん見てきました。
成績より大切なのは「幸せに生きていく力を育てる」ことなのです。
今回の記事のまとめ
- 親の愛情や期待は大切だが、行きすぎると子供を苦しめることがある。
- 知能や学歴が全てではなく、心の幸福が人生において本当に大切である。
- 子供の内面や希望・個性に目を向けた関わりが、長い目で見たときの幸福につながる。
- 「成功」よりも「納得できる人生」を一緒に見つけてあげる姿勢が親には求められる。
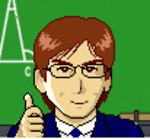
成績アップや志望校合格だけではない、「その先の人生」を意識しながら、親子で歩む中学受験を考えてみてはいかがでしょうか。